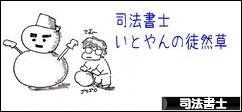池井戸潤の「下町ロケット」が文庫化されたので、昨日買いました。
今読んでいます。いやぁぁ、面白い!
「半沢直樹」のドラマにはまってから、「ロスジェネの逆襲」や「空飛ぶタイヤ」を読んで好きになっちゃいました。そして今回は「下町ロケット」というわけです。
今日、小説のことをブログで取り上げたのは、面白いなぁと思って小説を読んでいても、ついつい仕事と結びつけて考えてしまって、思うところがあったんです。
ちょっとネタバレになってしましますが、「下町ロケット」の中に高齢の弁護士が登場します。主人公が裁判に巻き込まれて、日ごろからお世話になっている高齢の弁護士に頼むのですが、どうやらその弁護士が扱った事のない高度に専門的な事件でした。
それで弁護士がいまいち上手く立ち回れないところを、主人公が指摘すると、その弁護士が言うですね。
「裁判とはそういうもの」「裁判がそんなものかわかっていない」

- 作者: 池井戸潤
- 出版社/メーカー: 小学館
- 発売日: 2013/12/21
- メディア: 文庫
- この商品を含むブログ (59件) を見る
このシーンを読んでいる時、ちょっと考えちゃいました。
こういう言葉はさすがに依頼者には言いませんが、心の中で思っているところは有るだろうなぁ、と。
主人公は、結局この専門的な事件が得意な弁護士に出会い、事件に上手く対処していきます。
小説の話ではありますが、主人公がもし得意な弁護士に出会わなければ「裁判とはそういうもの」と思って泣き寝入りするか、いろいろな弁護士に相談に回って「難しい」とか「和解した方がいい」とか言われる可能性があったわけです。
この業界では、民事トラブルなどで相談相手をとっかえひっかえして迷走する相談者を、相談難民といいます。相談した専門家から自分が納得いく回答が得られないがために回り続けるんですね。そのような相談者には「振り回されないように」とよく言われます。
しかし、自分が苦手な分野、勉強不足な分野を、「裁判とはそういうものです」「この事件は無理です」といって、相談難民とさせているのは、完全に専門家の責任です。
以前ブログにも少し書きましたが、相談時に相談者に専門用語を多用する弁護士・司法書士がたまにいらっしゃいます。先日、相談員をやっている時も、となりで「応訴管轄は…」「それは却下判決をもらって・・」「事物管轄は…」と民事訴訟用語を連発していらっしゃる司法書士がいらっしゃいました。隣で聞いてて、相談者は理解しているのか、心配になりました。
専門家は、「相談難民には気と付けろ」という前に「相談難民を作らない」という姿勢が大事なんだと思います。
うーん、真面目な話になっちゃいました。
↓2月用のバナーです。寒いですね。応援クリックをしてもらえると嬉しいです!あと、右下のB!はてなブックマークをクリックして頂くと、もっと嬉しいです!